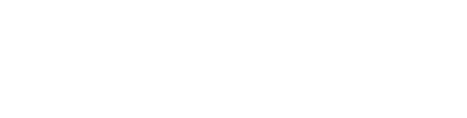地域に眠る“食財”を活用して“豊かな暮らし”の再生を! 河端 直之さんが語る瀬戸内

瀬戸内地方に関わりのある方に瀬戸内の魅力を語っていただく連載企画「ふるさとラバーズ」。
第15回目のゲストは、大阪府生まれ河端 直之(かわばたなおゆき)さん。
「瀬戸内国際芸術祭2016」の公認企画ドリンクの販売やメニュー・レシピ開発、イベント企画などを手掛ける「(株)せとうちのずかん」を経営。
小豆島をはじめとした瀬戸内での活動や瀬戸内地域の魅力についてお話を伺いました。
━━ 「せとうちのずかん」をはじめる前の、経歴についてお聞かせください
グラフィックデザイナーとして合計で約16年間、大手電機メーカーの販売助成物作成、その後、広告代理店で大手製薬メーカー通販事業のマーケティングやプロモーション戦略に携わってきました。 そうした経験を経て2010年に独立。
大きな企業をサポートするプロジェクトチームリーダーとしての経験を活かし、これからは小さな会社のお役に立ちたいと考え、現在は多種多様な業種の会社に対して販促プランナーとしてサポートしています。
独立後すぐに、カレンダー制作などの仕事をいただいていた大阪中央卸売市場 大阪市水産物卸協同組合に対し、サイトリニューアルのご提案をしたことがあります。ホームページを活用した認知拡大や理解促進のための情報発信の大切さをお伝えし、辛抱強く3年間、自主提案を続けサイトリニューアルを手掛けたことは、今ではちょっとした思い出です。
他にも、規格外だったりで売り物として難しい農産物に価値をつけていこうという取り組みや、鯨肉の専門店と鯨を食べる食文化を広める取り組みなどもしています。
こうして次第に食関連の仕事、会社や生産者との繋がりが拡がり、大阪をはじめ様々な地域での取り組みが繋がり、小豆島ともご縁ができるようになりました。
━━ 「せとうちのずかん」を立ち上げたきっかけについて、お聞かせください
「瀬戸内国際芸術祭2016」に向けて、2015年に瀬戸内国際芸術祭(https://setouchi-artfest.jp/)総合ディレクターの北川フラムさんが、観光に来た方のおもてなしや地域理解のために、食を充実させようという計画を提唱されました。
その計画を偶然目にし、小豆島の方にもご協力いただき企画に応募したところを採用いただき、「瀬戸内国際芸術祭2016公認企画」としてジュースを提供することになったんです。
それが「せとうちのずかん」の立ち上げのきっかけでした。

「瀬戸内国際芸術祭2016公認企画」で生搾りジュースを提供
━━ 「せとうちのずかん」がある小豆島について、お聞かせください
小豆島は、土庄町・小豆島町の2つの町からなり、海と山に囲まれ農水産業も盛んです。
島の大きな産業としては、オリーブ、そうめん、醤油、佃煮、ごま油の製造などをはじめ、観光業が大きな割合を占めています。

小豆島の景色
地域ごとに特性があって地域に根付いた産業が多く、季節の農水産物から多種多様な加工食品なども多くあって、食いしん坊にはたまらない場所だと思います(笑)。「せとうちのずかん」でも魅力的な食財をご紹介できればと、土庄町伊喜末(いぎすえ)のさつまいもをふるさと納税の返礼品として取り扱っています。
━━ 伊喜末での活動の経緯について、お聞かせください
伊喜末(いぎすえ)は海に近い砂地で、麦やさつまいも栽培に向いていたためか、かなり昔から盛んに行われていたそうです。
地域の方に聞いた話では、「ワシのじいさんの子どもの頃には、一面芋畑じゃった〜」とおっしゃっていたので明治の初めには既に盛んだったと思います。
ですが近年は人口減少が進み、生産者の高齢化などのため、さつまいもの生産量が急激に減ってきました。
伊喜末地域では、昔、さつまいも畑を耕すために牛を飼っていて、さつまいものつるを干して乾燥させ牛のエサにしていたそうです。
さつまいものつるを干すために、冬には「芋づるの塔」という風物詩があったのですが、今では牛を飼うことがなくなり、さつまいも栽培も減ってしまい、その風習も急激になくなってきたそうです。
現在は「陽当の里 伊喜末」という伊喜末地域の農業集団を中心に、この「芋づるの塔」づくりの文化を絶やさないようにと、地域の方たちと一緒になって毎年11月には地域イベントとしてつくり続けています。

芋づるの塔
他にも、「いもぎょうせん」という芋を煮詰めて作る水飴のようなものがあったと聞きますが、今では、島の中で作れる方が一人もいないそうです。
私は、食を大事に考えています。
その食の根幹にあるのは農水産業で、農水産業がある地域というのは、食にまつわる食習慣があって、文化として醸成され、伝統として引き継がれていくものと考えています。
伊喜末地域の「芋づるの塔」や種芋を保存する「いもつぼ」など、さつまいもにまつわる食文化や伝統を次の時代にも残していくために、伊喜末の方々が取り組む状況や話を伺い、古きよきものを守ろうじゃぁないんですけど、誰かが踏ん張らないと伝統が消えてしまうと考え、記憶として風習を残そうとしている方々のお手伝いが少しでもできればと「せとうちのずかん」の活動を伊喜末地域で始めました。
━━ 伊喜末地域での具体的な活動について、お聞かせください
まずは、「子や孫が戻って来れる地域にしよう、産業の根幹は農業」ということをお話ししています。
例えば、地域の農業がしっかりと続けば体験型のレクリエーションやアクティビティなど、自分たちの子どもや孫世代の新しい仕事に繋がり、地域の伝統を大切に守り続けていれば、次の産業としての魅力に繋がっていくと考えるからです。
子ども・孫たちに帰って来て欲しいからこそ、地域の産業の根幹である農業を頑張っていこうと。
2019年には地域での自主イベントとして、「芋掘り体験ツアー」を開催しました。
イベントを企画した当初は、「芋掘りでお金をいただくなんてできない」と地域の方々は考えておられましたが、都会の人たちのニーズやイベントの魅力について何度もお話しを重ね、「芋掘り体験ツアー」を無事に実施することができました。

芋掘り体験ツアー
現在は、産直イベントの自主開催や新商品開発なども積極的に行われるようになり、そういったイベントの開催が地域の活性化の一役を担えたのかなと考えています。
今、「せとうちのずかん」では、販路拡大のお手伝いができればと、さつまいもの受注や梱包・発送作業の窓口となり、農産物の販売を地域の魅力と一緒に取り扱えるようなお手伝いをしています。

地域の方との交流
生産したものがふるさと納税の返礼品となり、販路も拡大し、それがさらに地域貢献に繋がって、意欲やモチベーションアップにも繋がれば嬉しいですよね。その気持ちや手段自体も宣伝へと繋がっていくと思います。
━━ 「せとうちのずかん」の季節の生搾りジュースや小豆島産の食財を使ったお食事・特産品の販売について、お聞かせください
小豆島は、小さな土地で少人数でも収益をあげるための工夫をしています。例えば、1つの農家さんで、すもも・オリーブ・みかん類など様々な種類・品種の果樹や野菜を作り、一年中何がしらのものが収穫できるようにされていたりします。
そうした中で、「せとうちのずかん」店舗では、傷物やサイズの不適合などで規格外になってしまうような果物・野菜を活用し、観光で訪れてくれた方へ季節ごとの生搾りジュースをご提供しています。その穫れた地域や生産者、小豆島の風土などの話と合わせて、旬な食べ物の大切さなど産地の食財ならではの魅力もお伝えしています。
現在は島の食財を活用し、しっかりと味わっていただけるようなランチメニューもご提供しています。

小豆島の食材を使用したメニュー
━━ ふるらぶせとうちを見ているかたへのメッセージをお聞かせください
普段は商品開発や販路拡大のため、大阪や関東、小豆島を行ったり来たりしています。そのためか地域の違いなどがよく分かり、瀬戸内・小豆島のよいところを感じることができます。
瀬戸内エリアは平野部が少なく、住める地域も限られてきますが、その分すぐ近くには海があり山があり自然も豊かだし、気候も穏やかな地域なのでとても暮らしやすいと思います。人の存在もとっても近くに感じます。
季節ごとに、食財もたくさんあり、旬を感じながらの身体にも美味しい食事が魅力的ですね。
現在、小豆島では移住者を受け入れることに力を入れています。 年間300人ほどの方が移住してくださっているそうです。
小豆島は住みやすい、優しい、新しいだけではなく、自分のビジョンを持って、地域のことを大事に活かしてくれる方が、今後も増えていくといいなと思っています。
「せとうちのずかん」

〒761-4121 香川県小豆郡土庄町淵崎甲2130−6
農水産を大切にすることが持続継続可能な社会の根幹だと考え、これまでの繋がりや経験を活かし、持続継続可能な農水産業へのサポートを行う。主に、飲食店向けメニュー・レシピ開発のサポート、都市部物産館などへの特産品の納入、生搾りジュースや食事の提供など、地域に眠る“食財”を活用して“豊かな暮らし”の再生を目指す事業を行う。 ホームページ(https://www.setouchi-zukan.net/)

河端 直之さんプロフィール
大阪府生まれ京都・神戸育ち。グラフィックデザイナーとして、大手電機メーカーや大手製薬メーカーのマーケティングやセールスプロモーションに携わる。
食に関わる企業や生産者、飲食店のサポート、イベント企画などを経て、「(株)せとうちのずかん」を立ち上げる。持続継続可能な農水産業のお手伝いを続ける。